【Webツール紹介!】リキッドレイアウト対応の図形を出力するCSSジェネレーター
自社で作成したツール「Liquid Layout CSS Generator」の紹介です。 グラデーションを表現したり、綺麗な模様を描いたり、アニメーションを実装したりと、少し難しいCSS表現を簡単に出力してくれる「CSSジェネレーター」は、Web制作に携わっている方であれば何度かお世 ...
東京ホームページ制作
Copyright (c) BRISK All Rights Reserved.
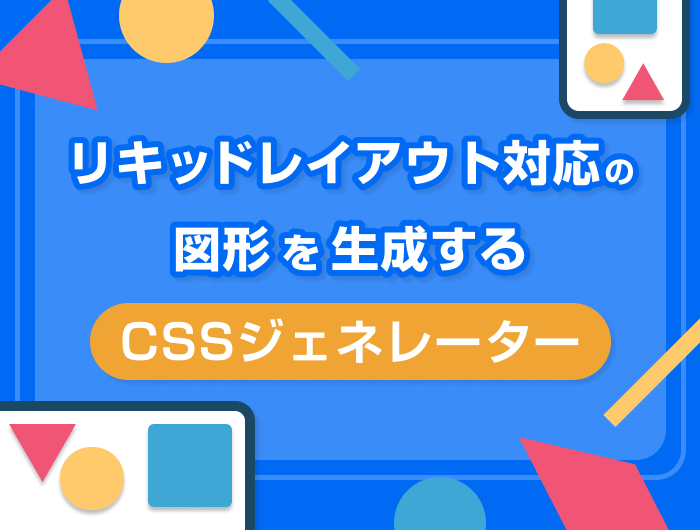
【Webツール紹介!】リキッドレイアウト対応の図形を出力するCSSジェネレーター
自社で作成したツール「Liquid Layout CSS Generator」の紹介です。 グラデーションを表現したり、綺麗な模様を描いたり、アニメーションを実装したりと、少し難しいCSS表現を簡単に出力してくれる「CSSジェネレーター」は、Web制作に携わっている方であれば何度かお世 ...
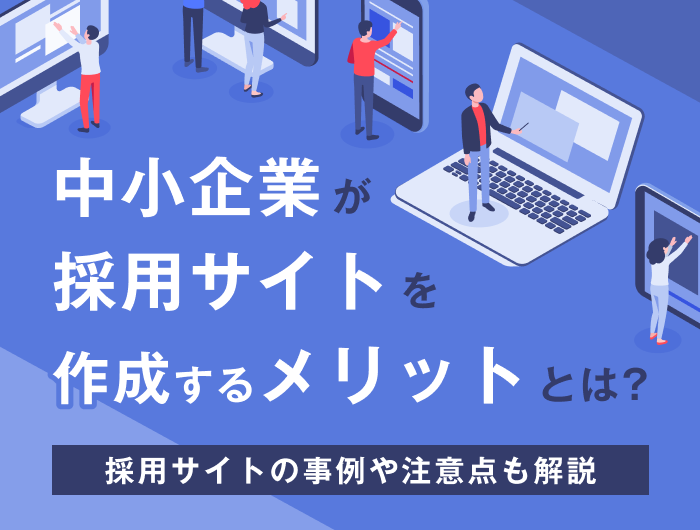
中小企業が採用サイトを作成するメリットとは?採用サイトの事例や注意点も解説
中小企業が採用サイトを作成するメリットを徹底解説。応募数や質の向上、採用コスト削減、ブランド強化など、採用活動を成功に導くポイントを事例とともに紹介します。 少子高齢化による労働人口の減少や採用競争の激化により、近年では中小企業にとって人材確保が大きな課題となっています。特に若年層を中 ...
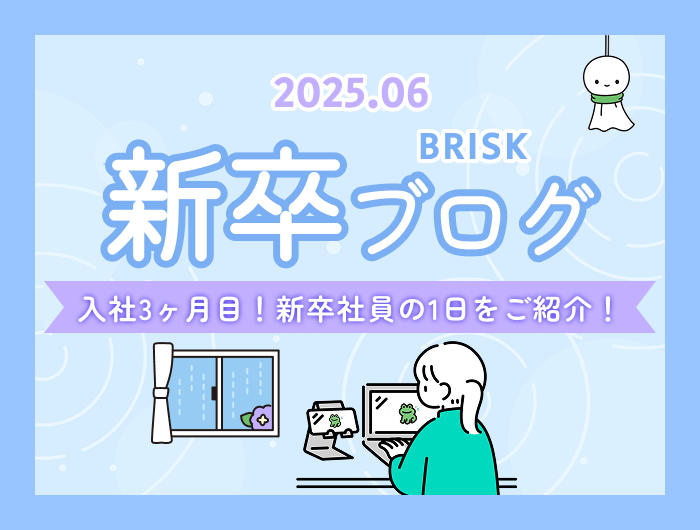
【2025年新卒6月】新卒BLOG~入社3ヶ月目!新卒社員の1日をご紹介~(Webデザイナー、Webエンジニア)
東京も先日梅雨入りしたはずですが、晴れの日が続いており、最近では30度を超える日も! 「もう夏なのでは?」と驚いています。暑さに弱い私としては、6月でこの気温だと、7月・8月がどうなるのか今から心配です…。 今月のテーマは「入社3ヶ月目!新卒社員の1日をご紹介」です。 あっという間に入 ...
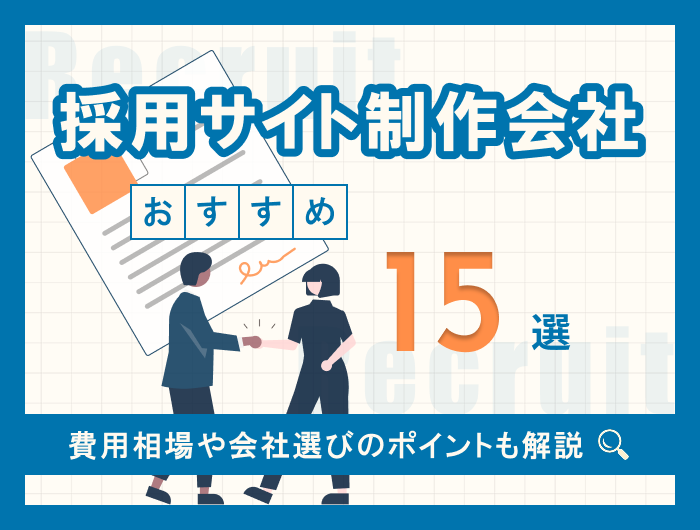
採用サイト制作会社おすすめ15選!費用相場や会社選びのポイントも解説
採用サイト制作会社のおすすめ15社を厳選紹介。費用相場や選び方のポイントも詳しく解説します。採用成果を高めるサイトづくりのヒントが満載ですので、参考にしてみてください。 企業の採用活動において、採用サイトは求職者との最初の接点となる重要な媒体です。求人情報だけでは伝えきれない企業の魅力 ...
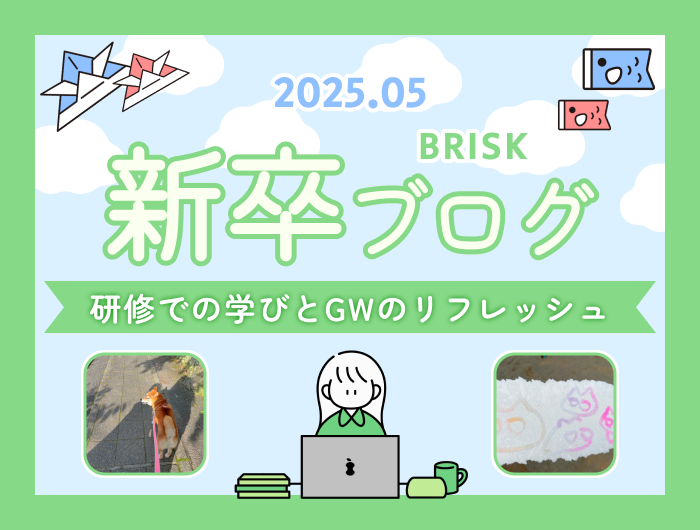
【2025年新卒5月】新卒BLOG~研修での学びとGWのリフレッシュ~(Webデザイナー、Webエンジニア)
ゴールデンウィークが終わり、気がつけばもう5月も中旬です。 だんだん暖かくなってきて朝晩の寒暖差にはまだ注意が必要ですが、外に出るのも気持ちいい季節になってきました! 今月のブログテーマは「研修での学びとGWのリフレッシュ」です。 4月半ばに行われた社内研修では、参加したメンバーに苦戦 ...
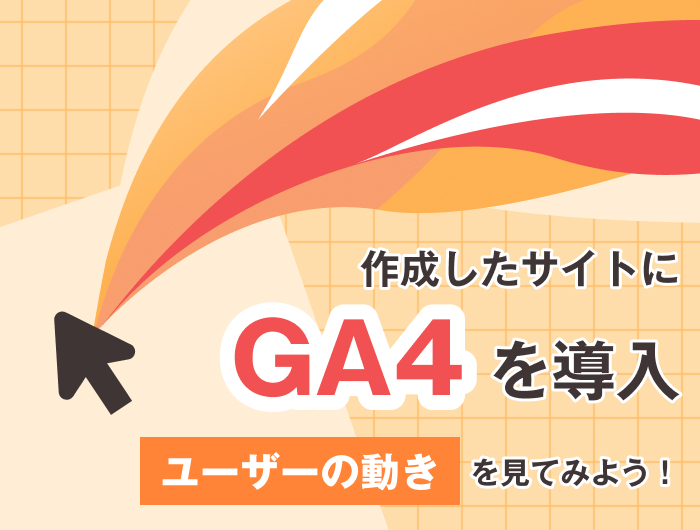
作成したサイトにGoogleアナリティクス 「GA4」を導入し、ユーザーの動きを見てみよう!
「サイトを作成したけれど、次に何をすればいいのかわからない?」という状況には、多くのウェブ制作者が直面します。 サイトの改善を進めるためには、ユーザーの行動データを活用することが重要です。 GA4(Google Analytics 4)は、ユーザーがウェブサイト上でどのように行動している ...
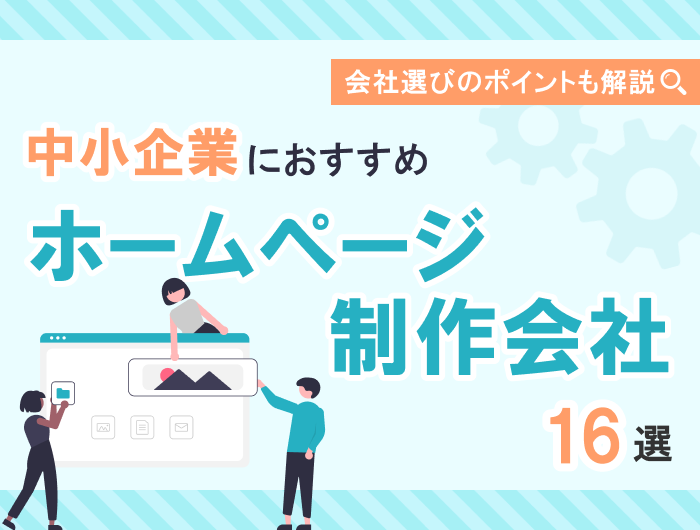
中小企業におすすめのホームページ制作会社16選!会社選びのポイントも解説
中小企業にとってホームページは、集客や信頼性向上、採用活動など多くのメリットがあります。本記事では制作費用の相場や補助金情報に加え、目的別におすすめの制作会社16社を厳選紹介。会社選びのコツも詳しく解説します。 「どのホームページ制作会社を選べば良いのか、また、費用や補助金制度の情報を ...

【2025年新卒4月】新卒BLOG再開します!~新メンバー紹介~(Webデザイナー、Webエンジニア)
この度、新卒ブログを再開することになりました~。 2025年度から新たに4名の新卒メンバーが加わりました! 新卒ブログでは、私たち新卒メンバーが感じたことや、日々の仕事の様子、そしてBRISKの雰囲気を少しでも伝えていけたらと思っています。同じように新卒として入社を考えている学生さん ...

font-familyの指定の仕方を解説!Androidで明朝体を表示させたい時の方法も紹介
みなさん、font-familyは正しく設定できていますか? font-familyはサイトに表示されるフォントを予め決めておくことができるCSSプロパティのことです。 いつも同じものを使っているためフォントを変更する際に指定を間違えてしまったり、テンプレートをそのまま使っているのでよく ...

ReactとNext.jsでウェブサイトを作る
本記事ではウェブサイトの作り方に悩んでいる人に向けて、ReactとNext.jsでウェブサイトを作る方法を紹介します。 ReactとNext.jsはプログラムの道具箱のようなもので、ウェブサイトを作るときに必要な部品が揃っています。 そのため、ウェブサイトをより効率的に開発することが ...
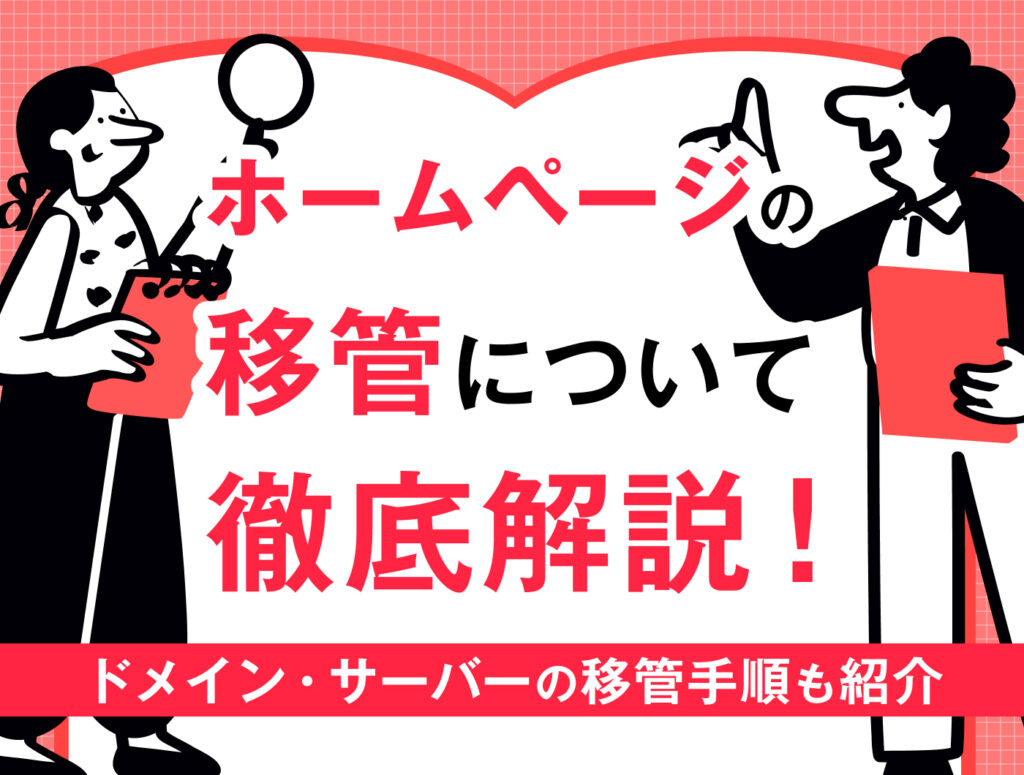
ホームページの移管について徹底解説!ドメイン・サーバーの移管手順も紹介
ホームページの移管は、サーバーや管理会社の変更に伴い、ドメイン、データ、メールアカウントなどの設定を移行する重要な作業です。このプロセスを適切に進めないと、サイトの表示や機能が停止するリスクが生じます。 そこで本記事では、移管作業の基本から具体的な手順までを詳しく解説します。現在の契約内容 ...

2025年の決意表明(社長日記 2025年1月)
あけましておめでとうございます! 1月も中旬を過ぎた所ですが。 1月はセミナーに多く参加させて頂く事からスタートし 考える時間を多くとる事のできた月でした。 2024年度の前半数字が思うように作れず 8割程の達成率で、それでも良いかな。と思っていた所もありましたが 数字が前年度を ...

IT企業・システム開発会社におけるホームページ制作を徹底解説!制作事例も紹介
IT企業やシステム開発会社にとって、ホームページは事業成長の「顔」となる重要なツールです。情報発信、顧客との接点強化、営業活動の補完など、その役割は多岐にわたります。しかし、「どんなホームページを作ればいいのか」「参考になる事例が知りたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。 そこで今 ...

IT企業・システム開発会社が求人サイトを制作するメリット|制作の流れからサイト事例まで紹介
IT業界の採用市場は、デジタル化や技術革新の進展に伴い、大きな変化を迎えています。優秀な人材を確保し、採用プロセスを効率化するためには、自社専用の求人サイトを構築することが重要です。 そこで今回は、IT企業やシステム開発会社を対象に、採用市場の最新動向や求人サイト構築のメリットを解説します ...

勤怠管理システムの費用対効果とは?算出方法から費用対効果を高める方法も解説
勤怠管理システムは、従業員の出退勤や勤務時間を効率的に管理するための重要なツールです。 手作業での管理に比べて、システムを導入することでデータの精度が高まり、労務管理の負担が軽減されます。 その結果、業務効率の向上やコスト削減が実現できるだけでなく、法令遵守の強化にもつながります。 今 ...
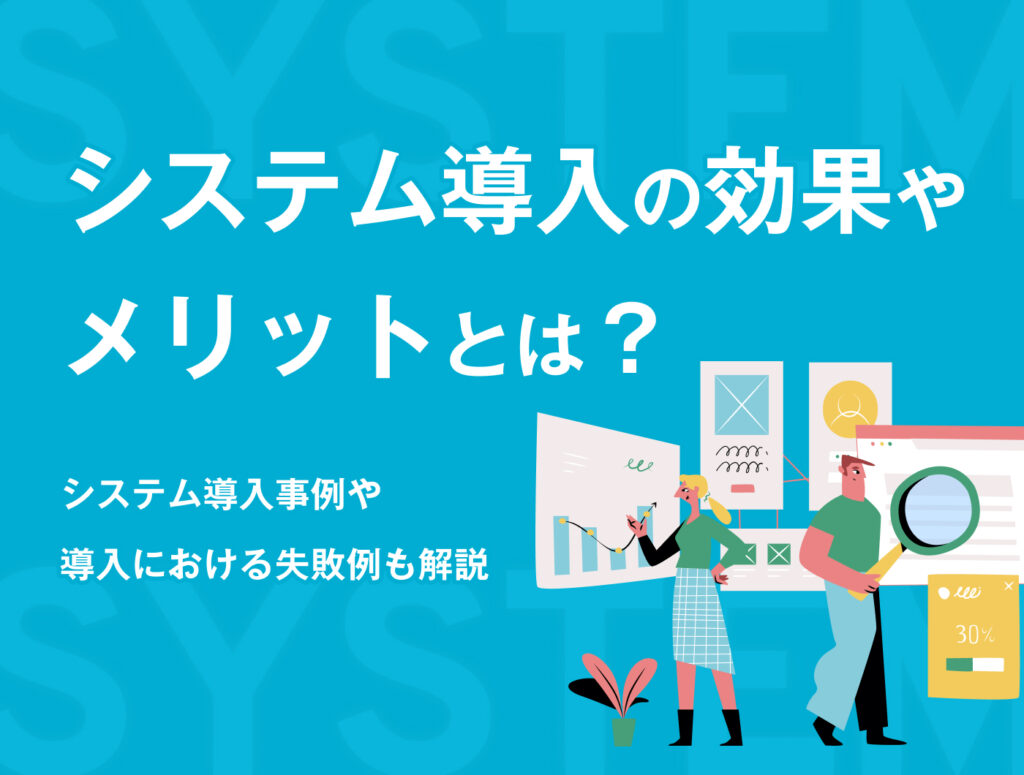
システム導入の効果やメリットとは?システム導入事例や導入における失敗例も紹介
システム導入は、業務の効率化やコストの削減、意思決定の精度向上など、多くの企業にとってメリットをもたらします。しかし、導入がうまく進まないと、期待していた効果が得られないことも少なくありません。 そこで今回は、システム導入の具体的なメリットや成功事例を詳しくご紹介します。 さらに、よくあ ...

ホームページの運用保守とは?作業内容や費用相場、外注時の注意点も解説
ホームページの運用保守は、企業の信頼性を保ち、集客を維持するために欠かせない作業です。運用保守には、サーバーやドメインの管理、セキュリティ対策、定期的なコンテンツ更新など、さまざまなメンテナンスが含まれます。これらの作業を適切に行うことで、サイトの安定稼働や検索エンジンでの評価を維持し、トラ ...
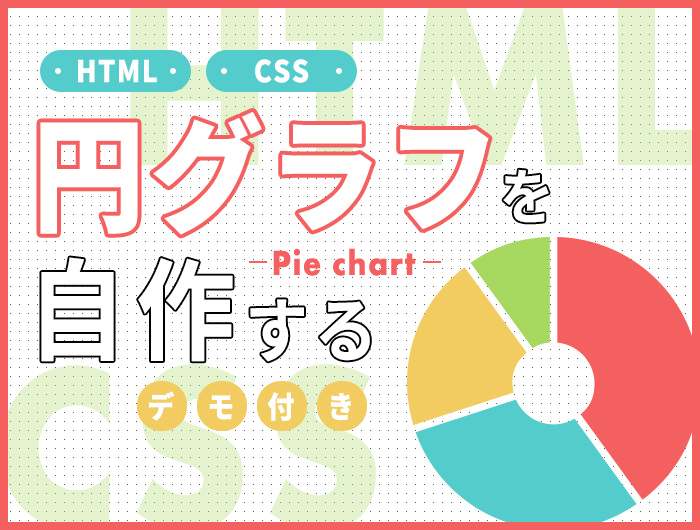
【HTMLとCSS】円グラフを自作する【デモ付き】
ウェブサイトにグラフやチャートを導入したいとき、様々な方法があります。 画像で配置したり、HTMLとCSSを使用したり、またはjsのプラグインでグラフを作成することができます。 ですが、画像で配置した場合はアニメーションを付けることはできませんし、jsのプラグインでグラフを作成する場合はデザ ...
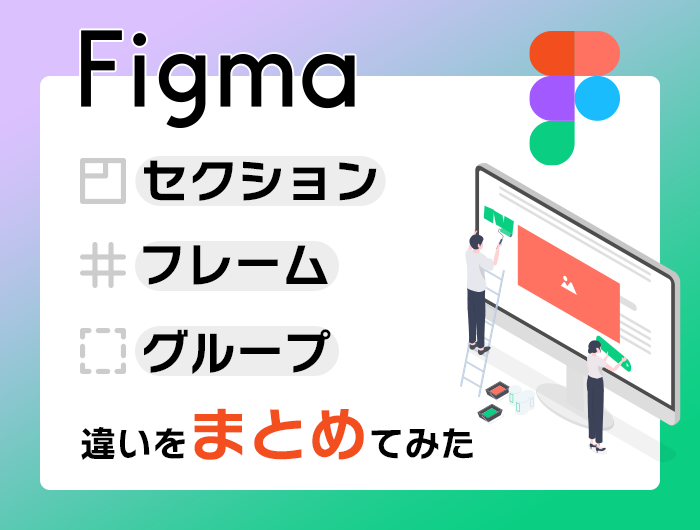
【Figma】セクション・フレーム・グループの違いをまとめてみた
日本語版も登場し、ブラウザベースのインターフェース・デザインツールとして大人気のFigma。 WebデザインツールといえばPhotoshopを長年使用してきた筆者にとって、 FigmaはAdobe XDよりも理解しやすいインターフェイスなので とても重宝しています。 なにより無料 ...

採用順調です!&more(社長日記 2024年7月)
ブログ久々に書きます! 昨日お客様に「ブログ見ました!」 なんて言って頂いて嬉しく久々に書くモチベーションになりました! ブログを書いてない期間が長いのでいろいろネタはあるのですが 今回は採用について書きたいと思っています。 25年新卒採用 なんとか目標としていた ...